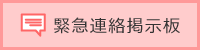名 称:桜川巡検
期 日:令和6年6月5日(水)13:00~16:30
場 所:桜川沿い(土浦市【小野、小高】、つくば市【北太田、北条、大貫】、筑西市【宮山ほか】)
講 師:大井信三 様(つくば里山研究会) 巡検協力者:小玉喜三郎 様(元地質調査所所長)
参加者:高教研地学部員ほか12名(講師含む)
行 程:「市立小町の館(土浦市小野)」集合→日枝神社(海浜礫の観察)→土浦市小高(海岸平野の痕跡)→つくば市北太田(桜川低地)→つくば市北条(海岸段丘)→つくば市大貫(桜川観察)→筑西市宮山(協和台地を眺望)→つくば市上菅間(河原の礫観察)→「市立小町の館」終了・解散
内 容
はじめに集合場所「市立小町の館(土浦市小野)」に設置された「山ノ荘ジオサイト」案内板で簡単な説明を受けた。その後、日枝神社の微高地及び海岸の痕跡を示す円礫を観察した。神社から少し離れた場所では露頭を観察することができ、扁平な円礫が地層中に多数見られた。これら堆積相から考察し、末吉海進時(約13万年前)の砂嘴や当時の海岸線の様子をイメージすることができた。
その後、つくば市北条付近の桜川低地へ移動した。現地でその幅の広さ(約2~3㎞)を目の当たりにすると、現在の桜川の規模で形成されたとは考えられないことが容易に理解でき、古鬼怒川と桜川との関係に興味が高まった。また谷中分水界の説明を受け、つくば市北条の谷中分水界を実際に通過し、地形の不思議な側面を再認識できた。なお、この時期の桜川の水位が高い(堰でダム化している)ため、中貫橋(つくば市大貫)でわずかに見られる現生河川堆積物を橋の上から観察し、現生の桜川を確認した。
最後に、宮山ふるさとふれあい公園(筑西市宮山)の高台から協和台地を眺望したのち、禊橋(つくば市上菅間)において桜川の河原でみられる礫の観察、堰や北条用水の歴史概要の説明を受けた。
今回の巡検は大井信三先生(つくば里山研究会)、小玉喜三郎先生(元地質調査所所長)の案内のもと、充実した内容で実施することができた。参加者一同、感謝申し上げます。なお、本巡検では、桜川の水位の関係で基調講演内容のテフラを観察することができなかった。桜川の水位が下がる9月以降、再び大井先生と小玉先生の案内のもと、テフラ巡検をぜひ企画したい。

日枝神社の微高地(神社の参道) 海岸平野起源の円礫の観察

桜川低地 現生桜川の河川堆積物(中貫橋)

宮山ふれあいふるさと公園の高台 桜川の河原でみられる礫(禊橋)